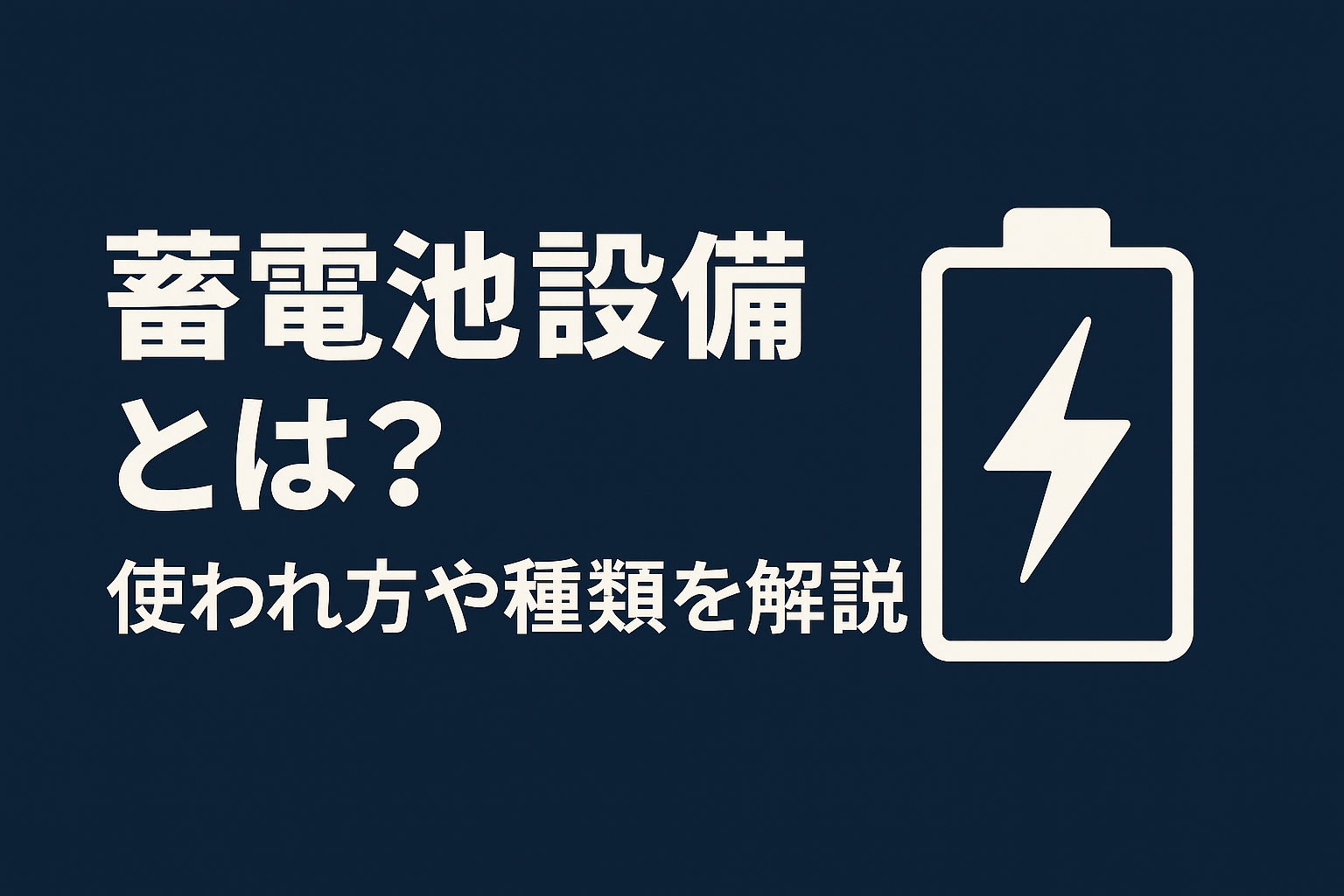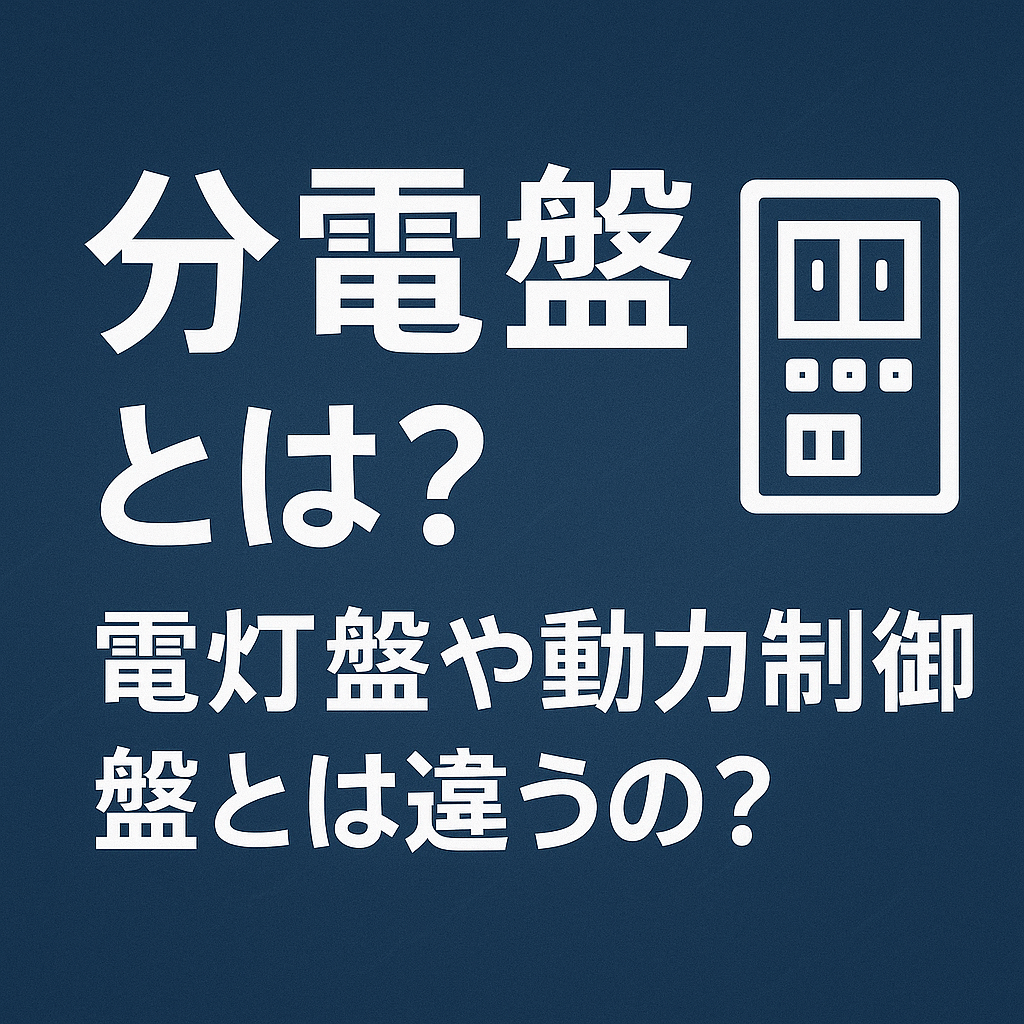災害や停電が起きた際、私たちの命や安全を守るうえで重要な役割を果たすのが「防災電源設備」です。日常生活ではあまり意識することのない設備ですが、ビルや病院、公共施設などの建築物には法律に基づいた設置が義務付けられています。
今回は、防災電源の種類、建築基準法・消防法との関わり、そして設計・管理における注意点について、事例を交えながら解説していきます。
1. 電源の種類:常用電源・予備電源・非常電源
電源には用途や稼働の優先度に応じて、いくつかの種類があります。
● 常用電源(商用電源)
最も基本的な電源で、電力会社から供給される商用電源です。家庭やオフィスの照明、空調、コンセントなど、日常的に使用するほとんどの設備はこの電源で稼働しています。
事例:
- オフィスビルの照明・エレベーター・空調
- 病院の診察室・ナースステーションの電源
● 予備電源(バックアップ電源)
常用電源が停止した場合に備え、一時的に電力を供給するための電源が予備電源です。UPS(無停電電源装置)やディーゼル発電機などが代表例です。
事例:
- データセンターのサーバールームに設置されている大型UPS
- 電車の変電所に設置された発電機
● 非常電源(防災用電源)
非常時、特に人命に関わる防災設備を稼働させるための電源が非常電源です。消防設備(自動火災報知器、スプリンクラー)や排煙ファン、避難誘導灯などを作動させるために使用されます。
事例:
- 火災発生時に自動で起動し、排煙ファンを動かす発電設備
- 地下街の非常灯を一定時間点灯させる蓄電池式非常電源
2. 防災電源とは?──予備電源の一種
防災電源は、電力が供給されない非常時に、防災関連設備を短時間でも確実に作動させるための電源です。
法律上では「予備電源」に分類されますが、特に防災目的に特化した機能と設置義務があるため、「防災電源」という言葉で区別されることが多くなっています。
【防災電源の主な役割】
- 火災報知器や非常放送を作動させる
- 避難用照明・誘導灯を点灯させる
- 排煙装置を稼働させ、避難経路を確保する
- 消火ポンプなどの消防設備を動かす
【一般的な構成】
- ディーゼル発電機:高出力で長時間供給が可能
- 蓄電池(バッテリー):瞬時起動と無騒音が特長
- UPS:サーバーなどの重要設備を一瞬も止めたくない場合に使用
3. 建築基準法における予備電源の設置義務
建築基準法では、建築物の用途や規模に応じて、「予備電源」の設置が義務付けられています。
特に「高層建築物」「地下街」「特定用途の建物」など、人の密集が想定される施設では、万一の電源停止時にも安全に避難が行えるように、予備電源の設置が求められます。
【建築基準法で定められた主な予備電源設備】
- 排煙設備(排煙ファン、排煙窓)
- 非常用エレベーター
- 非常照明設備
事例:
- 地上31階建てのオフィスビルでは、避難用の非常用エレベーターとその電源系統が建築基準法により設置義務
- ショッピングモールの排煙ファンにディーゼル発電機を接続し、常用電源断絶時も稼働可能にする
4. 消防法における非常電源の設置義務
消防法では、火災時に人命を守るため、防災設備を駆動する「非常電源」の設置が義務付けられています。
この法律では、火災報知設備や非常放送設備、スプリンクラーなどの消防用設備に対して、一定時間作動できる電源の設置が必要とされています。
【消防法で定められた非常電源設備】
- 自動火災報知設備
- 非常放送設備
- スプリンクラー
- 誘導灯・非常灯
事例:
- 病院では、停電時にもナースコールや火災報知器が使えるよう、バッテリー式の非常電源を設置
- 地下鉄駅構内の非常灯は、停電から10秒以内に点灯し、60分間保持する仕様に設定
5. 最小動作時間によって容量が決められている
防災電源の**容量設計で重要になるのが「最小動作時間」**です。
法律やガイドラインでは、防災設備を最低限何分間作動させなければならないかが明確に定められており、これに基づいて電源容量が決定されます。
【例:用途と最小動作時間】
| 設備名 | 最小動作時間の目安 |
|---|---|
| 排煙設備 | 15分以上 |
| 非常照明 | 30分以上 |
| スプリンクラー | 20分以上(建物による) |
| 非常放送設備 | 30分以上 |
【容量設計の考え方】
「必要出力(kW)」×「必要時間(h)」=「必要電力量(kWh)」
この計算によって、発電機の燃料タンク容量や蓄電池の容量が設計されます。
事例:
- 大型商業施設では、排煙ファン4台(各2kW)×15分=合計2kWhの電源が必要となり、UPSと発電機の組み合わせで構成
- 高齢者施設では、30分間の非常灯用に小容量のバッテリーを各階に分散設置して冗長性を確保
まとめ:防災電源設備は「命を守る最後の砦」
普段意識されることの少ない防災電源設備ですが、その設計や運用には法律に基づいた厳格な基準があります。特に建築基準法や消防法と密接に関わっており、災害時に命を守る最後の砦として機能します。
法的な義務だけでなく、自社のリスクマネジメントや**BCP(事業継続計画)**の観点からも、防災電源の整備・点検は非常に重要です。
建築や設備管理に関わる皆さまは、設計段階から電源の構成や容量、保守性までしっかりと把握し、万一に備えた「本当に使える防災電源」を整備しておきましょう。